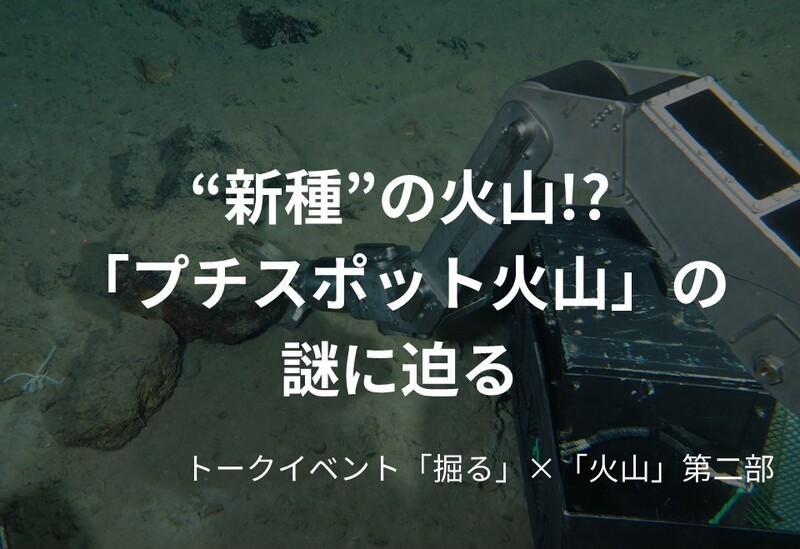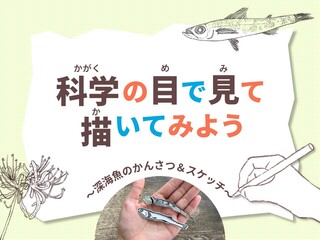皆さん、こんにちは!
科学コミュニケーターの倉田祥徳です。
ブログ前編では、「プチスポット火山」 について紹介してきました。後編では地球深部探査船 「ちきゅう」 を用いたプチスポット火山の掘削航海から秋澤紀克先生の研究内容までご紹介します。
ブログ前編はこちらからご覧ください。
https://blog.miraikan.jst.go.jp/articles/20250813post-567.html
「プチスポット火山」を掘る
今秋、地球深部探査船 「ちきゅう」 で掘削が行われるのは、東北沖から約200 km離れた海底にあるプチスポット火山です。

なぜその場所を 「掘る」 のでしょうか? そこから何がわかるのでしょうか?
秋澤先生によると、今回の掘削調査ではプチスポット火山を 「掘る」 ことで、いくつかの謎に挑もうとしているそうです。たとえばプチスポット火山は海側のプレート上にありますが、この火山がそのまま陸側のプレートの下に沈み込んでいく過程で、巨大地震の引き金になっている可能性はあるのか。また、日本列島に並ぶ火山たちとの関係はどうなっているのか。どのくらいの二酸化炭素を排出しているのか。こうした問いに、科学者たちは挑んでいます。

続いて、秋澤先生にこれらの疑問の手がかりとなる 「プチスポット火山の分布」 について詳しくお話しいただきました。
たとえば、チョコチップクッキーは上から見ただけでは中にどれだけチョコが入っているかはわからないように、プチスポット火山も海底を上から眺めただけでは、その全体像を把握することができません。
だからこそ 「掘って確かめる」 ことが重要だと秋澤先生は言われます。今回の掘削調査では、掘ることでプチスポット火山の全体像を把握し、プチスポット火山を形成しているマグマの量を正確に見積もることも、大きな目的のひとつとなっています。

もしかしたらプチスポット火山の中には、チョコチップではなく板チョコのような横に広がったマグマがプレート内部に形成されているかもしれません。もしそんなにたくさんのマグマがあれば、プチスポット火山のマグマには多くの二酸化炭素が含まれていることが知られているので (詳しくはブログ前編をご覧ください)、深海での火山活動が生態系に与える影響や地球全体の気候へのどんな影響があるのか、などにも大きな注目が集まります。ますますプチスポット火山から目が離せませんね。プチスポット火山の新たな発見に期待しながら、掘削航海をみんなで応援しましょう!
次は秋澤先生の研究内容についてご紹介します。
マントルのかけらを直接見る!
秋澤先生は、ふだん地球の深部にある 「マントル」 について研究されています。
マントルとは地球の表面をおおう 「地殻」 の下に広がる層で、深さ数キロメートルから数百キロメートルという、とても深い場所にあります。しかもマントルは非常に重い岩石であるため、地殻の上に出てくることはほとんどないそうです。そのため、私たちが “直接” マントルを観察するのは非常に難しいといえます。
では、どうすれば地球の内部にたくさん存在しているマントルを直接見ることができるのでしょうか。
そこで登場するのが、プチスポット火山です。
プチスポット火山の噴火にともなって、地球深部にあるマントルの “かけら” が、マグマに連れられて海底に現れることがあるそうです。そのマントルのかけらを 「しんかい6500」 で拾ってあげることで、マントルを直接見ることに秋澤先生は成功しています!

イベントでは、プチスポット火山周辺からマントルのかけらを発見したときの様子をご紹介いただきました。

このときは、まわりの黒色の物質が偶然剥がれていたため、マントルのかけらを発見できたそうです。これは研究者としてテンションが上がる瞬間だったと思います。秋澤先生がとても嬉しそうに話されている様子を見て、私も嬉しくなりました! 気になる方はぜひアーカイブ動画をご覧ください。
このとき採取したマントルのかけらは状態が良く、見た目もきれいだということで、イベント後に写真をいただきました。

さて、マントルのかけらを調べると、いったいどんなことがわかるのでしょうか。イベントでは2つの事例をご紹介いただきましたが、本ブログではそのうちの一つを取り上げます。
南太平洋のアイツタキ島で採取されたマントルのかけらを詳しく調べたところ、その中に含まれる鉱物から、「マントルのかけらが、かつてマントルの中を上下に移動していた」 ことが明らかになりました。たった一つの岩石から、過去の “上下運動” の痕跡をたどることができるなんて、驚きです! そして、このような運動を説明するには、マントルを構成する物質全体が、マントルの中で回転するような 「対流」 が起きていると考える必要があります。
私たちが見ている海は一見穏やかに見えますが、その下にあるマントルの中では、想像以上にダイナミックな動きが繰り広げられているのです。

ふだん見ることができない地球の “内部” の様子を教えてくれるマントルのかけらは、まるで地球から届いた “お便り” みたいですね。今度の研究で見つかるお便りにはどんなことが書かれているのでしょうか。地球の奥深くからのメッセージに、また新しい発見が詰まっているかもしれません。
最後に、イベント後のアンケートで寄せられた質問への回答を秋澤先生に後日うかがってきましたので、このブログで共有します!
~Q&A~
「どうやってプチスポット火山のCO2の放出量を見積もっているのですか?」
秋澤先生:プチスポット玄武岩の中には、マグマが急速に固まってできたガラスが見られます。そのため、このガラスのCO2含有量を分析することで元々のマグマのCO2含有量が推定できます。それとプチスポットの存在面積を考慮することでCO2放出量を見積もりたいと考えています。
「マントルまで掘れないのですか?」
秋澤先生:実は地球深部探査船 「ちきゅう」 は、マントルの深さまで届く長さのパイプは有しているんです。しかし、マントルは温度が高く、深いためその掘削は技術的に難しくなります。現在においては難しいですが、いつかはそのような日が来ると嬉しいですね!
「マントルのかけらは海底で採ったものと地表で採れるものは違うのですか?」
秋澤先生:海洋域と陸域 (特に大陸) では、採れるマントルのカケラの特徴は異なります。これまで、アクセスのしやすさから陸域のマントルのカケラは研究が進んでいました。一方で、海洋域のマントルのカケラは研究が遅れており、今回のプチスポット産マントルのカケラは海洋マントルの情報を多く我々に提供してくれると期待しています。
熱のこもったトークで観客を魅了されていた秋澤先生。ぜひ東北沖での掘削航海後に、プチスポット火山についてどこまでわかったのか、きれいなマントルのかけらは見つかったのかなど、お話をうかがいたいところです。研究成果を楽しみに待っています!
ブログ前編はこちらからご覧ください。
https://blog.miraikan.jst.go.jp/articles/20250813post-567.html