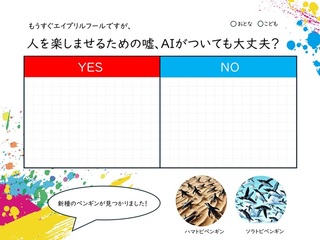はじめに
2025年9月15日、「量子って、いったいボクらのなんなのさ?#1暗号の新時代」を開催しました。日本科学未来館では同年4月に「量子コンピュータ・ディスコ」がオープン。今年は量子力学が誕生して100年を迎える国際量子科学技術年でもあり、まさに“量子の年”に量子技術について考えるシリーズイベントを実施しました。
今回は、量子情報技術(*1)の全体像をつかむとともに、とくに量子暗号(*2)という新しい暗号技術に焦点を当てました。登壇いただいたのは、大阪大学の山本俊教授と東京大学の小芦雅斗教授。いずれも量子暗号と量子コンピュータを専門とするお2人です。
*1 量子情報技術:重ね合わせや量子もつれなどの量子の性質を通信や計算などの情報処理に使う技術のこと。量子コンピュータや量子暗号通信、量子センサなどがある。
*2 量子暗号:メールやネットショッピングなど日々使うサービスでも大事なデータは暗号化されたのち、通信される。量子暗号は、現在の暗号化とは異なり、量子の性質によってより安全な通信を実現する暗号技術。

参加者のみなさんに、ワークや先生方のトークを通して、先生たちへの質問を考えていただきました。例えば、「世の中のセキュリティはすべて量子暗号に置き換わる?」「量子暗号が世の中に広まるのはいつ?」といった量子暗号に関する質問から「ある量子が量子もつれになっているかどうかをどうやって確認するの?」など量子に関する不思議まで、次々と質問が飛び出しました。登壇した先生には、イベント中多くの質問に答えていただきましたが、限られた時間で全てに答えることはできませんでした。
そこで、イベント終了後に控室で先生方に残りの質問への回答をうかがいました。このブログでは、その“延長戦”の内容をお届けします。量子暗号の現在地と将来について、より深く理解できる内容となっています。
…その前に、そもそも暗号って?
延長戦に入る前に、量子暗号を知るための基礎として、まず暗号とは何かを簡単に説明します。
暗号は、大切なメッセージを送る人と受け取る人以外の誰かに読まれないように隠すための道具であり、暗号化とは、メッセージを内容がわからないデラタメな文字列に変えることを指します。そして、デタラメな文字列を元のメッセージに戻したり、メッセージをデタラメな文字列に変えたりするために必要な情報を「鍵」と呼びます。鍵が簡単に盗まれたり、簡単に予測できたりする場合、その暗号は安全ではありません。つまり、暗号の安全性は、鍵の安全性に大きく依存しています。
量子暗号(特に量子鍵配送)は、この鍵を量子の性質を使ってつくり、共有する仕組み。量子には、盗み見ると状態が変わる性質や、予測不可能な完全なランダムを生み出せる性質があり、理論上極めて高い安全性が保証されています。
イベントの動画をご覧いただければ、延長戦がさらに理解しやすくなりますので、ぜひ。
延長戦スタート
中尾:
本番お疲れ様でした。これから延長戦として、残りの質問に答えていただければと思います。やはり、量子暗号の仕組みについて詳しく知りたい方が多かったようです。まずはこちらの質問どうでしょうか。
質問1
絶対解読できないとされる量子暗号は、量子技術が進めば解読できると思いますか?
質問2
量子暗号は、時間をかけても解読できないっていうのはなぜですか?
小芦先生:
結論からいうと、量子暗号は量子コンピュータが完成しても解読できないですね。
山本先生:
現代の暗号方式では、ある大きな数を使って情報を守っています。この数自体は誰でも見られるかたちで送信されますが、暗号を解くには、これを素因数分解する必要があります。この計算は今のコンピュータでは膨大な時間がかかり、現実的にはほぼ不可能とされています。だからこそ、今の暗号は安全だと考えられています。ただ、暗号化されたメッセージを何らかの方法で盗聴し記録しておいて、素因数分解が高速にできるようになったときに暗号を解読して、後からメッセージを読むことができてしまいます。そして、量子コンピュータが完成したら素因数分解にかかる時間は、ぐっと短くなると考えられています。
小芦先生:
従来の暗号は、計算量の観点から解読に非常に長い時間がかかることで守られています。その時間が天文学的な数字であれば、現実的には解読できないのですが、その数字が本当に天文学的かどうかは誰にもわかりません。つまり、安全性を正確に見積もることは難しいのです。
一方、量子暗号は、計算の難しさとは全く関係なくつくられていて、量子力学の原理そのもので安全性を保証しています。そのため、理論的に解読される確率は何百億分の一といった具合に、暗号装置ごとに安全性を数値として把握できるんです。
中尾:
適当にパスワードを入力して、たまたま当たっちゃうみたいなことは、どう考えればいいんでしょうか?
小芦先生:
例えば、パスワードが仮に4ビットしかなかったとします。その場合、適当に入力しても16分の1の確率で偶然当たってしまいます。(*3)これは暗号化しても必ず起こることです。このようなまぐれ当たりがあることと、量子暗号の安全性の話は別に考える必要があります。
量子暗号が実用化に向けて動きだした20年ほど前に、「量子暗号はどのくらい安全か」をどう定義するかで議論がありました。現在は整理されていて、「ε(イプシロン)-安全性」という指標で評価します。理想的な暗号を出力する仮想的な量子暗号装置と、実際に作った量子暗号装置を比較して、どのくらいその2つに原理的な違いがあるかを数値的に計算します。つまり、その値が100億分の1だとすると、実際の装置を使ったときにセキュリティが破られる確率は、理想的な装置を使ったときの確率と100億分の1しか違わない、という意味です。
ここで注意したいのは、これはパスワードのまぐれ当たりの確率ではないということです。4ビットのパスワードなら、完璧な量子暗号装置を使っても16分の1の確率で当たります。実際の量子暗号装置なら、先ほどの100億分の1の確率と合わせて、16分の1プラス100億分の1で破られる計算になります。その差はほとんどないですね。
*3 1ビットは、0か1の2通りの値を表現できる。4ビットなら、2×2×2×2=16通りの値が表現できる。
中尾:
なるほど。
小芦先生:
100億分の1という具体的な数字がちゃんと出ることで、リスクがちゃんと評価できる。現在の暗号方式の計算量的な安全性の場合は、そのリスクを評価する方法があまりありません。量子暗号は、原理的にリスクの量が計算できることは結構重要なポイントです。
山本先生:
100億分の1という安全性の値と、鍵の生成レートはトレードオフの関係にあります。安全性を高めれば、鍵を作るスピードが落ちる。そういう関係なので、リスクや用途、ユーザーのニーズに応じて調整できることができます。

質問3
生体認証が不安です。量子で変わることはありますか?
中尾:
次の質問ですが、生体認証と量子暗号って繋がりますか。
小芦先生:
「本当にこれが本人か」っていう、その確認に量子は関係ないですね。量子暗号は、メッセージを隠すという機能なので。暗号技術って、この人が本当に本人かどうかを確認するとか、単に秘密を読まれないようにするっていうだけでなく、いろんな機能を必要としているので、量子暗号は全てを解決できるような万能なものではないんですよね。
山本先生:
認証は、量子暗号を使わなくても十分だったりしますよね。
小芦先生:
そうですね。秘密にしておきたいメッセージは、20年、30年経ってから解読されても困るのですが、スマートフォンのロック解除や、オンライン決済のような本人であることを確かめる認証はその場で破られないことが重要です。だから、解読に非常に長い時間がかかることを利用する計算量で守る方式でも、実用には問題ないということがありますね。
質問4
量子もつれ(*4)は外から見ると壊れてしまうとのことですが、なんとかして間接的に見る方法はないのでしょうか?また、なぜ見ただけで壊れてしまうのでしょうか?
*4 量子もつれ:どんなに離れていても片方の量子の状態がわかると、もう一方の状態が確実にわかる、量子同士が相互作用した際に生じる非常に強い相関関係のこと。ただし、この関係はどちらか一方の状態がわかった瞬間に壊れてしまう。
山本先生:
量子もつれがなぜ見ると壊れるのかは、世界の仕組みとしか答えようがなくて、つまり、「なぜ世の中が量子力学に従うんですか」という根源的な話になってしまいますね。
小芦先生:
量子もつれは、直接でも間接でも見てしまったら壊れます。イベントの本番では、「量子もつれになっているかをどう確かめるのか」という質問があり、「実験的に測って確かめる」と回答しましたが、それは同じ量子もつれのペアがたくさんあるという前提が必要です。車の衝突検査みたいに、たくさんの量子もつれのペアがある中からランダムにピックアップしたものだけを測定します。そこで、量子もつれの相関関係が確認できれば、測らなかった残りも量子もつれになっているはずだと考えます。そういう仕組みを使って量子暗号は成り立っています。
質問5
トンネル効果(*5)はどんな手を尽くしてでも、マクロな世界で(人間で)はあり得ませんか?
*5 トンネル効果:身の回りの物理ではエネルギーが足りなくて通れない“壁”でも、量子は確率的にすり抜けてしまうことが知られている。半導体など多くの技術に利用される。
中尾:
目に見えるような大きいものの量子性を調べる研究は、行われていますか?
山本先生:
大きいものでも量子的な干渉をするかどうかって、ずっと研究されています。例えば、フラーレンでも干渉することが確認されています。大きいものでも、一応、波の性質はもっているんです。二重スリット実験という、粒子が波のように干渉する有名な実験がありますが、もしそれを人間で試す日が来たら…僕は、いくら安全だと言われてもそのスリットに入りたくないかも。(笑)
中尾:
そうですよね。(笑)
そのような研究のモチベーションや意義はどういった部分にあるんでしょうか?
小芦先生:
大きいものでも量子の性質が成立していることを確かめることには、とても意義があります。量子コンピュータに関連して、技術を高めていけば、大規模な量子系をコントロールできるわけですが、これはどんなに複雑にたくさんの量子ビットが関与しても、相変わらず同じ法則で量子もつれが起きるということで成り立っています。今の量子力学がどんなスケールでも必ず成り立っているっていう前提です。だけど、「それは本当か?」という話は常にあります。そんなに多数派ではないですけど。量子技術が進んで、たくさんの粒子が関与する量子現象を実験できるようになったときに、ある範囲からは今まで知られていない効果のせいで、量子もつれができなくなるとか、自動的に壊れちゃうとか、そういう議論もなくはないです。
山本先生:
誰も見たことないですからね。別に大きいもので量子もつれできないという理論はないから、できるはずならやってみないとね、というのはすごく真っ当です。そこに辿り着かないといけないと思っちゃうのが科学者という生き物ですよね。
中尾:
では、次で最後の質問です。
質問6
量子力学は将来どのような希望を世界に与えるのでしょうか?
小芦先生、山本先生:
これは良い質問ですね(笑)
山本先生:
今のテクノロジーの多くは量子力学の発見のおかげで成り立っているため、その意味では、すでに希望を与えているといえるかもしれません。僕らが話している量子情報技術ではどうかということですよね。
中尾:
そうですね。
山本先生:
情報技術の物理的な限界って、量子情報技術でおそらく決まっているのだと思います。なので、僕らに「何ができて何ができないのか」ということが量子情報技術の進歩によりわかるということです。それは結構すごいことなんじゃないかなって思っています。
小芦先生:
量子コンピュータの研究も、もともとは、我々が自然をどのぐらい意のままに操れるかっていう挑戦なんですよね。だから、知的な興味というか、山がそこにあるから登るみたいなことと一緒の気分です。
山本先生:
僕らの中ではそうですよね。科学としては必ずトライする領域。そのトライの中で見つかった技術で、恩恵を受けられる可能性が結構あるっていうだけでもお得だと思ってしまう。そんな感じですね。
中尾:
もともとは、量子というすごく小さなものをどれだけ精密にコントロールできるかみたいなそういう挑戦ってことですね。
山本先生:
それによって早く計算できることがあったり、安全になることがあったり、今まで見えなかったものが見えるようになるといったことが出てきています。研究するのは大変なんですけど、ワクワク感がある領域だと感じています。
中尾:
量子コンピュータなど具体的な技術やアプリケーションが登場して初めてその裏にある量子力学を身近に感じられると思うんです。これまで技術がなくてタッチできなかった現象に出会うと、「あ、世界ってこういう仕組みで動いているんだ」って実感できるかもしれない。技術を起点に世界の仕組みを目の当たりにすることが起きるんじゃないでしょうか。量子技術が社会に広がっていくことで、私たちの世界の見方みたいなものが変わっていく。そこが希望につながるといいんですけどね。
山本先生:
そうなるといいなと思います。いろんな人に使ってもらえることでいろんなアイデアが出てきたり、理解が深まったりするといいですよね。
中尾:
量子コンピュータが誰でも使えるようになったら、別に量子もつれとか不思議だとも何とも思わないっていう、そういう世代が出てくるかもしれないですよね。
山本先生:
最近は、それが当たり前であまり不思議に思わせないような教育をする方が良いんじゃないかっていう話もあったりしますね。
小芦先生:
大学レベルの量子力学の教え方はだいぶ変わってきていると思いますね。昔の量子力学の授業は、「たくさん実験をしたときに平均するとどんな結果になるか(期待値)」を計算することが授業のポイントになっていました。ですが、量子暗号や量子コンピュータでポイントになるのは、「確率」の考え方なので、今の授業では「一度の測定でどんな結果が出る可能性があるのか(確率)」を重視して学ぶようになってきています。
山本先生:
昔の授業だと「測定」という言葉があまり出てこなかったですよね。トランジスタなどの半導体部品を設計するときは、電子の振舞いを平均的に計算できていれば問題ないのですが、量子情報技術の発展によって、「測定」をちゃんと考えないといけないというように変わってきたんです。
中尾:
量子の教え方も時代とともに変わってきたんですね。
さいごに
量子暗号の仕組みから、量子力学の根底への疑問、そして社会実装や教育の話題まで、
参加された皆さんの多様な質問のおかげで非常に盛り上がった延長戦となりました。
技術が進むことで、いまは不思議としか感じない世界が少しずつ手の届くものになっていく。その変化を、私たちは今まさに体験しているのかもしれません。