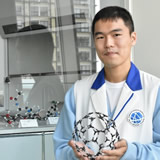先日、2025年度のノーベル賞受賞者が発表されました。受賞されたみなさま、本当におめでとうございます!
今年は坂口志文さん(生理学・医学賞)、北川進さん(化学賞)と、10年ぶりに日本人2名の同年受賞があり、メディアも大きな盛り上がりを見せていますね。
日本科学未来館では、3日間にわたり、生理学・医学賞、物理学賞、化学賞の受賞者発表の瞬間をみんなで迎える生配信を実施しました。ご覧いただいたみなさま、ありがとうございました。
受賞者の発表の後には、12月の授賞式という一大イベントが控えています。このブログでは、前回の記事に続き、私が今年6月に訪れたノーベル博物館の様子を交えながら、まだまだノーベル賞を楽しみたくなる情報をお届けします。

ノーベルウィークとは?
ノーベル賞の授賞式は、平和賞を除き、ノーベルの生まれ故郷であるスウェーデン・ストックホルムで行われます(平和賞の授賞式と晩餐会はノルウェーのオスロで行われます)。
授賞式が行われるのは毎年12月10日、アルフレッド・ノーベルの命日です。しかし、受賞者が参加するのは授賞式だけではありません。受賞者たちは授賞式の少し前からストックホルムに滞在し、さまざまな行事に参加します。
この1週間ほどの期間は「ノーベルウィーク」と呼ばれるのですが、そのなかで最初に訪れる場所がノーベル博物館です。
また、ノーベルウィーク中には、受賞研究の内容を紹介する「ノーベルレクチャー」と呼ばれる講義も行われます。受賞者たちが自らの研究を講演するのです。授賞式にだけ参加するのかと思いきや、大忙しですね。
カフェの椅子をひっくり返して、サイン
ところで、受賞者が椅子をひっくり返してサインしている光景を、ニュースなどで目にしたことはありませんか?

実は、ノーベル賞受賞者はこの黒い椅子の裏に記念のサインをすることになっていて、まさにこのサインが行われている場所がノーベル博物館なのです。
いくつかの椅子は、ひっくり返したり吊り下げたりして、サインが見えるように展示されています。日本人受賞者のサインも、複数見つけることができました。

さらに、一部の椅子はノーベル博物館のカフェスペースで使用されています。実際、私も半信半疑で無造作に置かれている椅子の裏をのぞいてみましたが……本当にサインがありました!
ノーベル賞受賞者がサインした椅子に座れるなんて、なんだか贅沢ですね。
受賞者の思い入れのある記念品を寄贈
さて、ノーベル賞の受賞者がノーベル博物館を訪れる目的は、椅子の裏へのサインだけではありません。受賞者たちは、博物館から記念品の寄贈を依頼されているのです。
というのも、ノーベル博物館の展示物のほとんどは、受賞者から寄贈された記念品です。現在、その数は300点ほどあるそうです。

記念品の選択は受賞者にゆだねられています。自由に選べるので、受賞研究に直接関係のあるものを寄贈する方もいれば、一見よく関連がわからないものを寄贈する方もいます。ただ、いずれにしても、受賞者の思い入れのある品が展示室に並んでいることは確かです。2点以上のアイテムを寄贈している方もいました。
ちなみに、ノーベル博物館ができたのは2001年の春。ノーベル賞設立100周年を記念して建てられました。そのため、それ以前のノーベル賞受賞者は郵送で記念品を送ったり、すでに故人となった受賞者は、その家族が記念品を選んだりするケースもあるそうです。
展示は「テーマ」ごと!
ノーベル博物館では、記念品を賞ごとや年度ごとではなく、テーマごとに展示しているのも特徴です。各賞あるいは各年度の記念品で分けるのではなく、Experimenting(実験)、Collaboration(協力)、Visualizing(可視化)などのテーマで分類しているんです。
たとえば、ニュートリノの研究でノーベル賞を受賞した小柴昌俊さんと梶田隆章さんは、ニュートリノ観測に用いる「光電子増倍管」という光センサーを寄贈していますが、これは“Collaboration”に分類されています。ニュートリノ研究は多くの人が関わり、国際協力も不可欠であることから、このセクションに展示されているといいます。

なお、直近1年間で寄贈された記念品は、入口近くの別のセクションに展示され、その後、各テーマに分類されます。ただし、記念品は毎年増えていくため、どこに配置するのが適切か迷うことも多いのだそうです。

記念品からわかる、研究者のパーソナリティとは?
寄贈される記念品には、研究者のパーソナリティが垣間見えるものもあります。
たとえば、2024年度に「コンピューターを用いた、タンパク質の設計と構造予測」の功績で化学賞を受賞したジョン・ジャンパーさんは、折り紙で作られた王冠を寄贈しています。

彼の研究チームは、タンパク質が折りたたまれる様子が折り紙に似ていることから、当初「折り紙チーム」と呼ばれていました。そして、チームでは誰かが成果を上げると、この王冠を贈り、次に大きな成果を出す人が現れるまでその人が持っておく、という習慣があったそうです。遊び心が素敵ですね。
また、共同受賞をしたデミス・ハサビスさんはチェスにまつわる記念品を寄贈しました。

彼は幼少期からチェスが大好きで、その経験を通じてコンピューターやAIに関心を持つようになりました。そうした背景が、タンパク質の構造を予測するソフトウェアの開発へとつながったそうです。
このように、ノーベル博物館では受賞者のエピソードも交えて記念品を展示しています。ぜひ現地を訪れた際には、気になる展示物についての解説もご覧になってくださいね。
ノーベルウィークもお楽しみに!
このブログでは、ノーベル賞の受賞者が最初に訪れる場所、ノーベル博物館を中心にご紹介しました。
今年、2025年のノーベルウィークには、きっと坂口さんや北川さんもノーベル博物館を訪れることと思いますので、どんな記念品が寄贈されるのかも楽しみですね。
次回は、ノーベル賞の授賞式や晩餐会についてご紹介します。12月のノーベルウィークに向けて公開予定ですので、ぜひご覧ください!