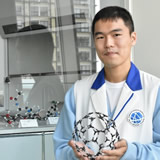みなさん、魚はお好きですか?
私は生き物全般が好きなのですが、中でも魚が一番。
少しだけ自己紹介をすると、私は小学校の頃に魚が好きになり、大学はそのまま海洋系の学部に進学しました。今は未来館の科学コミュニケーターとして、生き物をテーマにした科学コミュニケーションに取り組みたいと思っています。
私は見るのも、飼うのも、そして――やっぱり食べるのも好きですね。
皆さんはどうでしょう? 魚はお好きですか?
おいしい魚がいつでも気軽に食べられたらうれしいですよね。
万博に、魚の専門店?
さて、そんな魚好きの私が2025年6月、大阪・関西万博に出張することになりました。そこで 「特別な魚料理の専門店」 が出店しているという情報を見つけました。
お店の名前は――近畿大学水産研究所。
……水産研究所? 大学の研究所がレストラン?
気になったら行ってみるしかありません。というわけで、さっそく現地に訪れました。

近畿大学水産研究所
門をくぐり店内に入ると、魚たちの映像に包まれた空間が広がっていました。映し出されているのは、同じ種類の魚たちが群れ、それらが成長していく様子。これは、ただの海中風景ではなく、人の手で魚を育てている 「養殖イケス」 の中をイメージした空間でした。


席についてメニューを見てみると、「近大マグロ」 など、「近大〇〇」 といった魚の名前が並んでいました。
なんと、ここで提供されている魚はすべて、近畿大学で養殖された魚だそうです。

近畿大学は、水産養殖の分野で長年研究を重ねてきた大学。その研究の成果として育てられた魚たちは、実際に私たちの日常の食卓にも並んでいます。
つまりこのお店は、大学発の養殖魚専門のレストランだったわけですね。お店の名前にも納得です。
ただの「養殖」じゃない? 「完全養殖」とは
さらによく見てみると、ここで提供されている魚はただの養殖ではなく、「完全養殖」 とよばれる方法で育てられているとのこと。
この単語、大学時代に聞いた記憶はあるけれど……正直言えば、うろ覚え。せっかくなので、改めて完全養殖について調べました。
完全養殖とは、親魚から卵をとり、その卵を育て、成長した魚の一部をまた親魚として次世代に繋げる――というサイクルをすべて人の手で行う養殖方法です。つまり、天然の魚に頼らずに食用魚を生産する取り組みなのです。
近年では、過剰な漁獲 (魚の獲りすぎ) 、海の環境悪化、気候変動といったさまざまな理由により、天然の魚が減っていることが大きな問題になっています。その中で完全養殖は、持続可能な水産業の実現に向けたカギとなる技術として注目されています。
一方、完全養殖ではない養殖の場合、まず野生の稚魚や親魚を捕獲してくることから始まります。この方法では、種類によっては天然の魚を減らし続けてしまう恐れがあるとされています。
例えば、ウナギ。
土用の丑の日が近づくと、スーパーにずらりと並ぶウナギですが、パッケージに書かれている 「ウナギ (養殖) 」 が示すものは完全養殖ではありません。現在の養殖ウナギは野生の稚魚 (シラスウナギ) を捕獲し、それを育てて出荷するという方法で供給されています。つまり、出発点は天然の稚魚に依存しているのです。このままでは、私たちが食べるほどに、貴重な天然ウナギが減っていくという事態になりかねません。
実際、日本を含む東アジアに生息しているニホンウナギをはじめ、地球上にいる約16種のウナギの仲間の多くが絶滅危惧種に指定され、国際的な保全が求められている状況です。

「それなら完全養殖に切り替えればいいのでは?」 と思うかもしれませんが、ウナギの場合はそう簡単ではありません。
というのも、ウナギは卵を産ませること自体が難しく、さらに、生まれた仔魚 (しぎょ) の飼育にも非常に繊細な技術が必要です。
こうした数々の課題を乗り越えるために、日本でも長年にわたって研究が続けられてきました。
研究の結果、まだスーパーなどで見かけることはありませんが、一部の研究機関ではウナギの完全養殖に成功しています。現在は、より効率よく安定的に生産できるよう、さらなる研究が進められているところです。
……といった感じに完全養殖について思い出しながら、「おいしい魚を楽しみながら、天然の魚も未来に残せたら素敵だなあ」 などと考えつつ、私はメニューを眺め、料理を注文しました。
店内には水槽展示も!
料理を待つ間、ふと店内を見回すと、水槽があるではありませんか。海洋系大学出身としては、これは見逃せません。解説パネルを読んでみると、この水槽で泳いでいる魚たちも、実際に近畿大学で養殖された個体とのこと。中にはニホンウナギの水槽もありました。

こちらで展示されている個体は、天然の親ウナギから採取した卵を人工的にふ化させて育てたものだそうです。これは完全養殖の一歩手前の技術。さらにここから大人になったウナギに卵を産ませ、次世代につなぐことで完全養殖となります。
近畿大学では、2023年にニホンウナギの完全養殖に成功し、現在はより効率的に生産できるように研究を行っているとのことです。近い将来、近大で育てられた完全養殖ウナギが私たちの食卓に並ぶかもしれませんね。

水槽にはこんな魚も!

右:「シマアジ」 ギラっと光る流線型の体が美しい
マダイは完全養殖技術が確立されており、各地の養殖場から出荷され、私たちの食卓でもおなじみの存在です。近畿大学は古くからその品質向上に取り組み、マダイ養殖の発展に長年貢献してきました。
シマアジはアジ科に属する高級魚で、近畿大学により完全養殖技術が確立されました。お寿司にしても焼き魚にしても絶品の魚です。

右:「タマカイ」 この個体もシャイだったので頭をひょっこり出した瞬間を撮影
クエはハタ科の高級魚。大型になる種で、クエ鍋などで知られています (筆者はそんな高級料理は食べたことがありませんが……)。タマカイはハタ科の中でも特に大型になる魚で、サンゴ礁域など暖かい海に生息しており、こちらも食用に漁獲されています。
これら大型のハタ科魚類は、繁殖が可能になるまで時間がかかるため、獲りすぎてしまうとすぐに数が減ってしまいます。そこで、資源を守りながら需要にも応えるため、完全養殖の研究・実践が進められています。

クエの完全養殖技術は確立されたものの、出荷できるサイズに育つまで成長が速い個体でも4年もかかるのが課題でした。その課題を解決するため、開発されたのが交雑種 「クエタマ」 です。これは、クエを母親に、クエよりも成長の早いタマカイを父親として人工的に交配させた魚で、クエのような味わいを備えつつ成長スピードが2~3倍も速いとのことです。
このように、分類的に近い異なる種の魚を交配させると、より産業的に優れた個体をつくり出せることがあり、近年注目されています。近畿大学では、こうした魚を 「サラブレッド魚」 と名付け、お店のメニューとしても提供されています。
もちろん、こうした交雑種の活用には、慎重な準備と管理が必要です。
例えば、万が一これらの魚が自然の海に逃げてしまうと、生態系に影響を与えてしまう心配があります。そのため、水槽を使った屋内での養殖など、自然に影響を与えない工夫が進められています。
お料理を実食!
さて、水槽を見ているうちにお料理が運ばれてきました。ここからは、いただいたお料理から完全養殖の魚たちをご紹介します。
近大マグロ
近畿大学の養殖研究の目玉といえば、やはり 「近大マグロ」 。こちらはマグロの中でも特に高級なクロマグロの完全養殖個体です。
クロマグロは、成長すると2~3mにもなる大型魚で、卵を産めるようになるまでに3~5年かかります。一方で、その高い人気ゆえに、若い個体が大量に漁獲され、1990年代以降、20年ほどで激減しました。
こうした背景の中、おいしいマグロを食べながら守っていくために始まったのが、完全養殖の取り組みです。とはいえ、クロマグロの完全養殖は並大抵のことではありません。長期にわたる管理、大量のエサ、広大な飼育スペースが必要です。また、生まれた子どもは繊細で育てるのが難しい魚でもあります。
このような理由から、クロマグロの完全養殖は長年“夢”とされてきましたが、2002年に世界で初めて近畿大学が完全養殖に成功。「近大マグロ」 と名付けられました。


それでは実食。気になるお味は……おいしい! マグロ類は種類によって味わいが異なりますが、近大マグロもクロマグロらしい脂の風味をしっかり感じられました。
ちなみに現在、クロマグロは漁獲量や漁獲サイズの規制などにより、資源量が回復傾向にあるとされています。
天然資源の回復を喜びつつ、完全養殖の技術も並行して磨いていくことが、クロマグロを未来に残していくうえで大切なのかもしれません。
サラブレッド魚
別の種の魚を交配させた品種 「サラブレッド魚」 もいただきます。


お刺身は、左下がブリヒラ、右上がクエタマです
クエ (雌) とタマカイ (雄) の交雑種 「クエタマ」 は、濃厚な旨みがありつつ、身がしっかりしています。ブリ (雌) とヒラマサ (雄) の交雑種 「ブリヒラ」 は、ブリよりもコリコリとした歯ごたえがあり、さっぱりとした旨みを感じます。筆者はブリしか食べたことがありませんが、この味わいの違いは交雑種ならではかもしれません。

ごちそうさまでした!
完全養殖のこれから
今回、完全養殖の魚を食べながら、ふと考えたことがあります。それは、「いつでもおいしい魚が食べられる」 というのは当たり前ではないのかもしれない、ということです。
今、私たちにとって身近な魚も、さまざまな問題に直面しています。獲りすぎ、生息環境の悪化、気候変動……これまで豊かだった海の恵みが、未来でも同じように続いていく保証はありません。
そして、その現状をつくってしまった私たちにも、きっと責任があります。
そのような状況の中で、おいしい魚を楽しむことと、天然の資源を守ること、その両立をめざす技術のひとつが 「完全養殖」 なのだと思います。すでにいくつもの魚種で研究が進み、成果も出てきています。
もちろん、課題もあります。
例えば、生産コストの高さ、生態系への影響、そして消費者である私たちがどう受け入れていくかなど、生産する魚種によっては、まだ発展途上の部分も多い技術です。そのような課題にも目を向けながら、これからも完全養殖の研究に注目していきたいと思いました。
まだまだ知りたい完全養殖
今回、完全養殖された魚を味わいながら、養殖技術や水産業の未来について考えるきっかけを得ることができました。同時に、新たな疑問や興味もたくさん出てきます。
例えば、あの巨大なクロマグロをどうやって人の手で一から育てているのか?
マグロだけでなく、マダイやシマアジなど、完全養殖が可能になった背景にはどんな研究や工夫があるのか?
そして、こうした研究が進むことで、未来の海や私たちの食卓はどう変わっていくのか?
などなど……。
知りたいことは尽きません。本やインターネットで調べつつ、「いつか研究者の方に、実際にお話を伺ってみたいなあ」 と思う私なのでした。