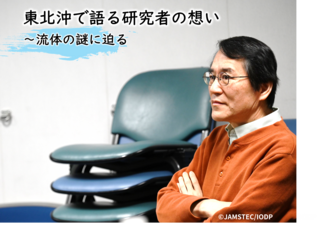皆さん、こんにちは!
科学コミュニケーターの倉田祥徳です。
地震がいつ起こるかは、誰にも想像することはできません。
2011年3月11日、東日本大震災が発生したとき、私は宮城県仙台市に暮らしていました。当時は高校生で、津波警報が鳴って、全校生徒職員が屋上に避難したことを今でも覚えています。まさか自分が、巨大地震を経験するなんて、これっぽっちも思っていなかったのが正直なところです。そんな経験もふまえて、「もしも明日、地震が起こったら?」という具体的な問いをテーマに、防災イベント「考えてみよう! 明日地震が起こったら?」を2025年3月8日(土)と 9日(日)に開催しました。
このイベントでは、はじめに常設展示「100億人でサバイバル」の解説ツアーと、防災準備について考えるワークショップを行いました。その後、ドームシアターにて、仙台市天文台が制作したプラネタリウム番組「星よりも、遠くへ」を上映しました。このブログではそれぞれの様子をみなさんにお届けします。
常設展示「100億人でサバイバル」の展示解説ツアー
5階の常設展示「100億人でサバイバル」は、地震や感染症、気候変動など、現代社会におけるリスクとどう向き合うかをテーマにしています。今回は特に「地震」にフォーカスし、科学コミュニケーターが展示を案内しました。

ツアーのなかでは紙芝居型の解説も用意し、地震が起きるメカニズムや海底に設置されている地震計などについても解説しました。

解説のなかで意識したのは、防災を「非常食や飲料水の備蓄」といった物理的な準備にとどめず、家族との連絡手段や避難先での生活の工夫など、「暮らし」の視点からも捉えることでした。また、「災害が冬に起きたらどうするか」といった具体的な状況を想定した備えについてもお話ししました。
参加者からは、「防災リュックは用意していたが、季節を考えていなかった。防寒対策の重要性に気づいた」「休日に災害が起きた場合のことを想定していなかった」といった声が寄せられ、ふだんとは異なる視点で防災について考える機会になったのではないでしょうか。
また、展示ツアーのラストでは「もし地震が明日起きるとしたら、何を準備するか?」という問いを投げかけ、次のパートであるワークショップへの思考の橋渡しを行いました。
ワークショップ「もしも、明日地震が起こったら?」
展示ツアーのあとは、7階の会場へ移動してワークショップ「もしも、明日地震が起こったら?」を実施しました。
「明日の15時、震度7の地震が起こったとき、あなたは何を持っていたいですか?」という問いが書かれたワークシートと、「もしもプロジェクト」という団体が作成した災害が起こった後に何が必要になるのか、何を備えるべきなのかまとめた「もしもの100」という資料を配布し、災害時には、何が必要になるのか一緒に考えました。

参加者は5分ほどの個人ワークを通じて、自分が本当に必要とする“備え”について考えます。例えば、小さなお子さんがいる人にとってはミルクやおむつ、ペットを飼っている人にとってはエサや避難場所の確保が重要になります。また、寒い季節であれば、防寒具やカイロも欠かせません。
その後はグループに分かれて、書いた内容をお互いに見せ合いながら意見を交換しました。「思っていたよりも、自分に必要なものって人と違うんだ」「“缶詰を少し高級にしておく”ってアイデア、たしかに気分が落ち込んでいるときにはだいじかも」など、会話を通して“他者の視点”から学びや気づきが生まれていくのが印象的でした。

ワークショップの終盤では、「フェーズフリー」という考え方も紹介されました。フェーズフリーとは、想像することが困難な非常時に対して備えるのではなく、日常時のいつもの生活で便利に活用でき、 非常時のもしもの際にも役立つ商品・サービスを利用しようという考え方のことです。

解説では、フェーズフリーの具体例として、外出先で雨や雪に濡れた紙にも書けるボールペンや、ふだん使いができる超撥水のトートバッグ(災害時にはバケツに変身します!)などを紹介しました。こうしたアイテムは、日常になじみながらも、いざというときに頼りになる“備え”として機能します。

また、身のまわりのものでフェーズフリーになりそうなものは? という問いかけには、ある来館者から「おもちゃ箱を災害時は非常食の入れ物にする!」という意見が出ました。このようなワークショップを通じて、防災が特別な準備ではなく、日常の延長線にあるものとして意識できた人も多かったのではないでしょうか。参加者一人ひとりにとって、地震への備えをより現実的に考えるきっかけになっていたように思います。
プラネタリウム番組「星よりも、遠くへ」
ワークショップのあとは、ドームシアターに移動してプラネタリウム作品「星よりも、遠くへ」を鑑賞しました。この作品は、東日本大震災の夜に被災地で見上げられた星空と、その体験を語る被災者の言葉をもとに構成されたドキュメンタリーです。
会場が暗転し、ゆっくりと星空が広がっていくなかで語られたのは、あの夜、避難所で見上げた空のこと。水も電気もないなかで、頭上に広がる星空が、ほんの少しの安心や希望を与えてくれたこと。ある人は夜空の明るさに驚いたといい、またある人は星を見ながら「明日も生きよう」と思えたと語っていました。
出てくることば一つ一つに意味を感じながら、東日本大震災が起きた日のことを振り返りました。
上映後はアンケートと感想を別々に書いてもらい、感想はホワイトボードに貼ることで、他の参加者と間接的に意見を共有することができました。その一部を抜粋してご紹介します。
「停電のせいで美しく輝く星空、非情だと最初は思ったけれど、その星空になぐさめられた方も多かったのだと分かりました。美しい星空を見たいと思いました。」
「とても悲しい出来事だったのに、宇宙を視点にした時、心が広がる感じでした。大自然の中に生きていて、自然にあらがうことはできない複雑な気持ちです。」
「今まで星は綺麗なものとだけ思っていたけれど、同じ景色を見ている人をつなぐだけではなく、亡くなった人と生きている人もつないでくれるものだと、捉え方が変わりました。」
「人は星空の下で生者や死者あるいは自身と向き合うことができる。震災について災害について命について考える際には静けさが必要で、明かりも欲しい、そう思った」

地震はいつ起きるかわかりません。でも、いざというときの備えは、日々の暮らしのなかで始められます。家族で話し合ってみる、バッグの中身を見直してみる、ふだん使っている物の中から災害時にも役に立つものを見つけてみるなど、できることはたくさんあると思います。
このブログが “日常の中の防災” を考えるきっかけとなり、普段の暮らしの中でできる備えに目を向けていただければ幸いです。