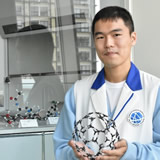このブログは、疲労と休息がテーマの特別企画「ツカレからの脱出 ~疲れとやすみのサイエンス」(2025年7月16日~9月15日)の様子をお届けするブログシリーズです。これまでのブログはこちら。
vol.1 自分らしく休んで、疲れとさようなら https://blog.miraikan.jst.go.jp/articles/20250808post-566.html
vol.2都会の中の小さな森のやすらぎ ~デジタル森林浴~ https://blog.miraikan.jst.go.jp/articles/20250808post-565.html
vol.3 未来館「イス」めぐり https://blog.miraikan.jst.go.jp/articles/20250812post-564.html
疲労と休息がテーマの特別企画「ツカレからの脱出 ~疲れとやすみのサイエンス」。これまでのブログでは展示を中心にお伝えしてきましたが、この企画の一環としてさまざまなイベントも行っています。今回のブログはその第一弾、2025年7月19日に開催したイベント「もしも、あなたのそばに “シンコキュウ” があったら……」の様子をお届けします。
このイベントのテーマは、ずばり「呼吸」。呼吸法インストラクターの資格を持ち、後ほど紹介する“シンコキュウ”というデバイスを開発した三好賢聖さんをお招きし、呼吸の不思議な性質と、それをもとに開発したシンコキュウというデバイスについてご紹介いただきました。

呼吸の「社会性」をみなさんも体験!
イベント開始早々、三好さんは「呼吸の不思議な性質をみなさんに体験してもらうので、ペアをつくってじゃんけんしてください」と言いました。一体どんな体験をしたのかをこれから書いていくので、ぜひこのブログを読んでいるみなさんもペアを見つけてじゃんけんしてみてください。
まず、じゃんけんをして負けた方は、30秒程度息を止めてみてください(持病をおもちの方や妊娠中の方、体調がすぐれない方は、相方に役割を交換してもらってください)。そして、じゃんけんに勝った方は、息を止めている人を「見て」ください。何も考えずに、ただ「見る」だけでいいです。
(写真の下にネタバラシがあるので、ここでいったん画面を閉じてやってみてください。)

息を止めた方、苦しかったですよね。お疲れさまでした。
では、息を止めている人をただ「見て」いた方、息を止めるよう指示されていないにもかかわらず、息が止まっていませんでしたか?
この実験は2012年に発表された論文で実際に行われた実験の一部で、息を止めたり息切れすることが他者にうつってしまうことを示しています*。つまり、呼吸は自分だけのものではなく、ほかの人と共感しあうものである――このことを三好さんは「呼吸には『社会性』がある」と言います。
* Masaoka, Y. et al. (2012). Sharing breathlessness: Investigating respiratory change during observation of breath-holding in another. Respir. Physiol. Neurobiol. vol.180, p.218-222.
https://doi.org/10.1016/j.resp.2011.11.010
また、共感についてはこちらの科学コミュニケーターブログもご覧ください。
人間を科学して行き着いたのは? ──未来館の常設展示より https://blog.miraikan.jst.go.jp/articles/20171030post-144.html
このあと、息を止めるかわりに深呼吸をし、相方がそれをただ「見る」実験も行いました。こちらもただ見ているだけなのに、相方が深呼吸をする動きについ共感して、気づいたら意識せずとも深呼吸できていたという声が多くあがりました。

人とモノの間に生まれる“共感”
ここまでは、人と人のあいだで呼吸が共感することについて紹介してきました。では、その共感は、人とモノのあいだにも生まれるのでしょうか?
三好さんが開発に携わったデバイス「シンコキュウ」はこのような問いのもとでつくられています。カギとなるのは、人がモノの動きについつられちゃう性質(運動共感)。たとえば、上昇しているエレベーターを外から見ると、自分の体が少し上がるような感覚になったり、思わず息を吸ってしまったりしませんか? シンコキュウはこのようなヒトの運動共感を利用してつくられた、大きなマカロンのような見た目のデバイスです。このうち上の部分(マカロンでいう上側の生地の部分)がゆっくりと上下に動くことで、さりげなく呼吸のリズムを伝えてくれます。

イベントでは、シンコキュウの動きを見ながら深呼吸をする体験を行いました。すると参加者から「ほかの人が深呼吸しているのを見たり、自分が深呼吸しているのを見られたりするより、気まずさが減った」という感想が出ました。たしかに、見たり見られたりする気まずさはみなさんも感じたことがあるかもしれませんし、たとえば街中でよく見かける「目」が描かれたポスターはその気まずさを活用したものといえるでしょう。一方、呼吸のリズムをモノとして置いておくシンコキュウは、図らずもそういった気まずさをおさえることができているのかもしれません。

呼吸を意識することは「オトクな心のつかい方」
イベントの最後に三好さんから、いい呼吸が私たちの生活に与えるメリットについてお話しいただきました。呼吸のリズムを整えていい呼吸を行うことは、睡眠の質や免疫力、集中力を高めることにつながります。しかもその効果は自分だけでなく、相方がただ「見る」実験からわかるように、自分の呼吸を見たまわりの人にもおよぼされるのです。だから呼吸は、自分がちょっと気をつけることで多くの人にいい影響を与える「オトクな心のつかい方」なんだと三好さんは言います。みなさんも、ふだん何気なく行っている呼吸をほんのちょっと意識してみてはいかがでしょうか?
このブログではイベントの内容を中心に、呼吸の不思議な性質とシンコキュウというデバイスについてご紹介してきました。ただ、これらについてはまだまだ語り切れていないことがたくさんあります。気になる方はぜひ、未来館のポッドキャスト「ミュージアムの片隅で未来を雑談するラジオ」の#32を聞いてみてください。